更新日:2025年8月28日
医療情報部
医療情報部の紹介
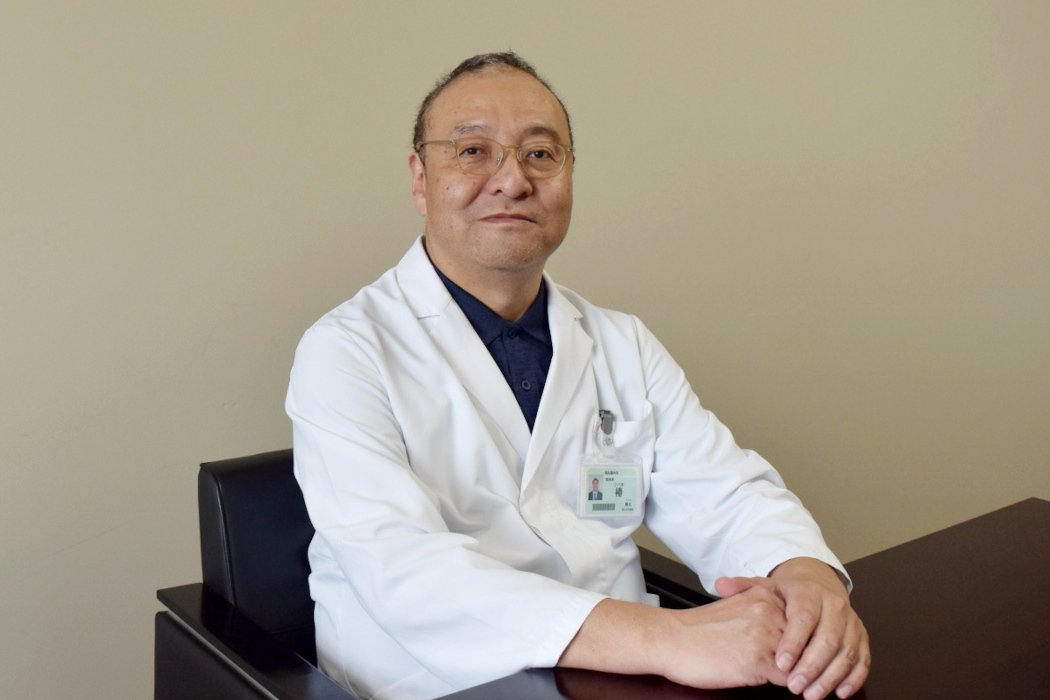
- 医療情報部長
椿 雅光
(つばき まさみつ)
当院の医療情報部は、「診療情報病歴室」「電子カルテ運用管理室」「ネットワーク運用管理室」の3室で構成され、診療記録や医療情報の適切な管理・活用、電子カルテシステムの安定した運用、そして院内ネットワークの安全かつ円滑な維持管理を統括しています。私たちは、診療を支える「情報の中核」として、システム・セキュリティ・業務改善の観点から、現場の声に寄り添いながら、日々の運用支援と継続的な改善に取り組んでいます。
診療情報病歴室
- 診療記録の電子・紙媒体の管理
- 医療統計・がん登録・診療記録の開示対応 など
電子カルテ運用管理室
- 電子カルテシステムの運用管理・マスター管理
- ベンダーとの調整、セキュリティ対策 など
ネットワーク運用管理室
- 院内・外部ネットワークの安全管理
- グループウェアやインターネット環境の整備・運用 など
医療情報部の取り組みと実績
医療情報部では、電子カルテの安定稼働や情報セキュリティ強化に加え、以下のような業務改善・現場支援を積極的に進めてきました。
- 電子カルテバージョンアップやセキュリティ強化
- スマート外来案内システムの運用支援とLINE通知の活用
- 病理・放射線レポートの見落とし防止対策の運用 など
医療DX
医療情報部では、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に推進し、最新技術を導入することで、より質の高い医療サービスの提供と業務効率の向上に努めています。
電子署名の発行
同意書などの重要な文書を、紙での保管だけでなく、電子カルテ内でも安全に管理しています。
電子化された文書には電子署名を付けることで、「誰が、いつ、何を記録したか」が正確に残り、書面と同じ法的な効力を持つようになっています。これにより、情報の正確性と信頼性が高まり、患者さんにとっても、より安全で質の高い医療提供につながっています。
RPA(Robotic Process Automation)による業務自動化
医療現場でも、多くの定型的な事務作業が発生します。医療情報部では、こうした反復的な業務を効率化するため、RPAを導入し、人的リソースの最適化に取り組んでいます。
RPAは、人が行っていたデータ入力や帳票作成などのルーチンワークをソフトウェアロボットが代行する仕組みで、ヒューマンエラーの低減や作業時間の短縮に効果を発揮します。令和7年現在、院内28の業務プロセスがRPAによって自動化されており、医療職や事務職の負担軽減を可能にしています。
- 医療相談業務効率化を目的とする「医療相談管理シート」作成への取り組み
- 業務の効率化と自動化を目指したDX(Digital Transformation)の活用 - 褥瘡対策診療計画書の入力不備への取り組み -
遠隔診療の実施
地域医療連携の一環として、遠隔診療を導入し、地理的制約を超えた医療サービスの提供に取り組んでいます。愛媛県立南宇和病院の診察室と当院の診察室をWEB診療システムで接続し、遠隔地からの診察を可能にしています。これにより、専門医が常駐していない場合でも継続的かつ質の高い診療を受けられるよう支援し、患者さんの通院負担を軽減するとともに、地域全体の医療アクセス向上を図っています。
IoT器機の導入支援
在宅医療や外来診療におけるIoT器機の活用が広がるなか、医療情報部では、厚生労働省が示す「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の観点から導入支援を行っています。
【参考事例】- CGM(持続血糖測定)機器
- 腹膜透析(PD)管理
- 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル用制御装置 監視
診療録自動要約AI「Laplace(ラプラス)」のご紹介
医療従事者の業務負担軽減を目的に、当院では独自にオフラインで稼働可能なAIによる診療録自動要約AI「Laplace(ラプラス)」を開発・導入しました。
日々の記録業務を支え、医療の質と業務効率の両立を目指す新たな取り組みです。


